一番大切なものはその人にしかない何かしらの「ユニークネス」だと思うんです。

晩秋の静かな長谷の海岸。堀内さんは少し照れながら写真を撮られている。仕事柄人の話を聞いたり、写真を撮ったりすることは多いのだそうだが、自分が被写体になることには慣れていない…といいながら、朗らかな笑顔だ。
「子どもが生まれて都内から引っ越したんですが、鎌倉には特に縁はないんです。子ども時代をどんな土地で過ごしたかというのは、人生を左右する大事なことだと思うので、子育てする場所にはこだわりました。妻は海辺育ちで、僕は山の中で遊んで育ったので、海も山もある鎌倉なら理想に近いねって意見が一致して。子どもの保育園は浜に近いので、しょっちゅう海で遊んでいるみたいです。」
八王子の山育ち
子ども時代のほとんどを八王子の山の中ですごした。多摩ニュータウンが造成中の時代で、高台から見下ろすと、造成地が住宅に変わっていく姿を刻々と観察することができたそうだ。
「子どもながらにニュータウンの町が開発されている様に関心していました。暗くなって山の上から見下ろすと、遠くに見える町の灯がともるエリアが日に日に広くなっていくんですよ。」
学校が終わるや小さな天狗のように、学校仲間とつるんで近所の里山を走り回り、秘密基地づくりや探検に勤しんだ。
「家がある住宅地は、小高い丘のほぼ頂上にありました。頂上は公園と貯水池になっていて、周囲の里山と連なっていく。子どもだったから意識はしていなかったけれど、登ったり、降りたりしながら丘にしたら2つか3つくらいの範囲を走り回って遊んでいた記憶があります。住んでいた近くの自然はまるで我が家のようで、隅々まで知りつくしていました。日が高い内は家に帰らないで、真っ暗になるまで外にいたなあ。八王子は都内近郊ですけど、自覚的には山育ち、野山を駆け回った子ども時代でした。もしこの7年がなかったら、今の自分はなかったと思います。」

「調度僕が育った八王子の里山も、こんな感じに緑がワシワシ生えていました。なんとなく似てるんですよ、この付近は。」長谷から極楽寺に抜ける切通にて。
八王子の山からマンハッタンへ強制連行!?
何も考えなくても幸せそのものだった小4までの山生活から、堀内少年は突然引き離されてしまう。家庭の事情で吉祥寺に転居することになり、その後まもなくアメリカに移住したのだ。
「アメリカに連れていかれた、今でもついそう言ってしまうのですが、なんだかよくわからないうちに八王子の山の中から、NYの郊外へ吹き飛ばされた感じです。アメリカに行くより前に、いったん吉祥寺に移動したのですが、まずその時のインパクトが大きかった。当時は八王子に自分の世界や友達や大事なものをすべて置いて、引き離されてしまったという感じがしていました。」
メーカー勤務の父の仕事の都合でNY郊外の住宅地に住むことになる。一家は両親と2つ上の姉、生まれたばかりの弟の5人家族。子どもたちは地元の公立小学校に入り、言葉もわからないまま、マンハッタンのベットタウンで3年を過ごす。
「アメリカに行ったことで僕は帰国子女になった。英語が操れる、外国生活を経験しているゆえの独特の雰囲気をまとうに至った。日本社会では特殊な扱いを受ける運命にはまってしまったというか。僕自身にとっては、実は語学よりも、マイノリティとして生きるという経験をしてしまったことが考え方を変えました。アメリカの現地でも、大多数が話す言葉が話せない、前提条件が違う。八王子ではもちろん、吉祥寺でさえ山育ちというだけで、外国人ではなかった。でもアメリカでは自分だけ違う。それ以来、自分だけ違うということに違和感を感じなくなりました。いい意味で人と同じでなくても恐怖を感じなくなった。
アメリカでは授業で国語の輪読をするんですけど、先生は僕だけスキップするんですよ。どうせ読めないから、いないみたいな扱いで。嫌だったけどしょうがない、わからないんだから。もちろん外国人のためのESL(English as a Second Language)という特別授業もあるんだけど、差別されるのが悔しくて、そこに甘んじる気にはなれなかった。勝負できるジャンルで、日本の方が進んでいる算数や、体育と芸術科目はがんばりました。サッカーでは地域のクラブにも入っていて、州の大会にも出ましたし、音楽ではビオラをやっていて、NYのプロ楽団のジュニア部門に推薦されたりもしました。」
八王子時代から音楽好きの母の影響で家にはグランドピアノがあり、ピアノを練習していた。元々音楽が好きだったことで、アメリカ生活でも少しは溜飲を下げることができたようだ。母方の祖父は戦前から活躍するプロの画家で、80代をすぎて取材旅行に行ったインドで体調を崩し帰国後に亡くなった、死ぬまで現役を通したアーティストだった。
「祖父の影響は大きいですね。家の中の母の教育方針でも、クリエイティブなスタンスを暗に求める雰囲気があったと思います。父はメーカー勤務でしたが、外国語系の大学を出ていて、読書家で、蔵書も多かったし、カルチャー色の強い家ではあったかな。僕の気質は祖父ゆずりだと思います。あの年代の人としてはオープンな人で、遊びに行くとヒゲでほおずりされたり、抱きしめてくれたりと、愛情表現が豊か、考えていることをなんでも言葉にする人だった。逆に父は普段から何を考えているかよくわからない人で、そういったら『男はやたらに思ったことを言うもんじゃない』みたいなことを言われました。僕とは違うタイプなんですよ、父は。」
あいつが帰ってきたらしいぞ!
日本に帰国したときは中学2年になっていた。吉祥寺で数か月在学した小学校からそのまま進学する地域の公立中学に編入したのだが、彼の帰還は噂になって広がったそうだ。
「実は、八王子の山育ちと都会の少年たちはフィーリングが合わなくてですね、適応する間もなくマンハッタンだったのですが、渡米前に事件を起こしたんです。転校生だからとクラスメイトにいじられて、大げんかになり、僕はあまりにも頭にきて小学校から脱走しまして。行方不明になって、パトカー出動の大騒ぎになりました。偶然にも同日近くの公園で水死体があがるという事件も重なり…数年ぶりに有名なあいつが帰ってくるらしいぞ・・・みたいな、編入当時はザワザワしていたみたいです。」
日本の高学年と中学前半をアメリカで過ごしたこともあり、学力にはむらがある。強かったサッカーもアメリカの指導と日本のきめ細かな指導では違いがありすぎ、技術的に差がついていた。パッとしない中学後半をやり過ごしつつ、受験勉強に取り組み、東京近郊の私学では最難関のひとつICU高校に進学する。
「帰国子女がほとんどで、世界99カ国から学生が集まっていて、気が楽でした。みんな同じような境遇だから、他人を気にせず自分らしくやりたい放題に過ごしていました。興味があることをとことん。サッカーはやめてしまって、バイト三昧。音楽にシフトしたのも高校時代で。スナフキンみたいにいつもギターを持っていて、学年にいた音楽バカと組んで「ゆず」のカバーをしたり、作詞作曲したり。高校生らしくラブソング作ったり、世の中に言いたいことを詩に書いたりしてました。」
そのまま内部進学し、ICU大学では3年生から主専攻を決めるシステムだったので、金融工学を専攻することにした。進学した当時は大手銀行の倒産事件や、外資系企業の台頭もあった。会社がお金で売買されたりすること、お金の世界で起こる事の仕組みに興味があったし、教授がとてもユニークで世界を金融のフィルターで見るという世界観にも惹かれた。金融業界で働く先輩たちの勇姿も魅力的だったし、就職にも有利だろうという計算もあった。
「大学時代は勉強もしましたけど、ほとんどフリスビーに注力していました。アルティメットというフリスビーを飛ばして、相手の陣地にパスをつなぐスポーツです。軌道を見たり、風力を計算したりするのが面白かったし、男女混合なので、大学生活を謳歌するにはぴったりでした。」
基準はあくまで面白いか面白くないか
楽しい学生生活を送り、就活も苦労しなかった。内定の入った大手都市銀行に迷いもなく入行、しかしそれは世間を知らない若造の大失敗だった。
「金融工学を活かせる分野で学卒の募集がなかったので、都市銀行の営業職で就職しました。研修は長くて、実務をこなしながら、ゆっくり鍛えるシステムだったようです。でも体育会系的な上下関係とか、寮生活を強いられたりするような軍隊風のやり方に耐えられず、8か月で辞めてしまいました。就活の時から父は『銀行は合わないんじゃないのか』と心配してくれていました。父は長いメーカー勤務で銀行とも付き合いがあるし、僕みたいな男は銀行には向かないって見抜いていたんですかね。」
父の心配をよそに堀内さんは順調に転職を果たす。今度は外資系企業の日本法人で、日本で開催する国際見本市を企画運営し、海外から参加者を集める仕事だった。英語ができる、営業が多少できるという条件で、問題なく仕事を始めることができた。とにかく海外に行きたいという意向もあり、入社して3ヶ月で早速海外に飛んだ。
「見本市の仕事はすごくシンプルで面白いビジネスなんです。ひとたび開催すると開催地にたくさんの人が訪れ、経済効果があります。出展企業や来場者だけじゃなくて、開催された都市に波及効果が大きいのが面白いところです。仕事内容は主に、日本企業と海外企業の出会いの機会をセッティングすることですが、いろんな国の複数の業界の人と親しくなり、よくしていただきました。一年の1/3は海外を飛び回る生活で、楽しくてしょうがない感じでしたね。
いろんなジャンルの仕事を手掛けましたが、新エネルギー部門では太陽電池や水素電池、スマートグリットなんかを扱っていました。国際色が豊かで動きの速い業界で、毎年各国のメーカーから新しい技術が発表される場面に立ち会えて、とても面白い仕事でした。そういう交渉力についても、この時期イベント企画の仕事を通して自信がつきました。5年くらい順調で、評価も年収も上がり調子でハッピーだったはずなんですが、ふと思うところができて、会社を辞めました。
海外営業をしていると、海外のメーカーが日本の展示会に出展するのは、金銭的にもマンパワー的にも大変なチャレンジだということがわかってきます。相当な覚悟で来日した海外企業の方に対して、イベントやってお疲れさまじゃあまりに深みがない。イベントビジネスというのはそういうものなのですが、人と関わっているうちに、イベントがらみだけではなく、企業のグローバルビジネスに関わる仕事がしたいと思うようになりました。」
コンサルティングファームに転職後、訳あってコーチに転身

堀内さんお気に入りの極楽寺駅そばのカフェHarenovaにて、とびきりおいしいドーナツで有名
堀内さんは次の仕事としてコンサルティングファームを選んだ。そこがたまたま海外ライセンスを管理する、語学力があって海外営業ができる人材を探していたのだ。うまくはまって転職したが、堀内さんを引っ張った上司が突然退職するなど、転職するなり会社での立場が微妙になってしまう。コンサルプロジェクトを手がけつつ、経営企画寄りの仕事をしていたが、浮いたスタンスで難しい局面をうまく切り抜けることがなかなかできず、ついに精神的に追い詰められて体調を崩し、休職することになった。
「孤軍奮闘で追い詰められて、辛いとか不安だとかいう感情を押し殺して生きていたんですね。一番つらい時代にお世話になったエグゼクティブコーチにそう言われました。『君は人間なんだよ、感情があるのが当たり前なんだよ。辛いことは辛いと、受け止めないとつぶれちゃうよ。』当たり前だけれど、それさえわからなくなっていました。もともと楽しいことや興味のあることにどんどん進むのは得意なんですが、自分の中の暗い部分、ネガティブな感情に向き合ってこなかった。
ある時全身にじんましんが出て、薬を飲みながら会社に行ってたんですが、ふと、こんな風にいやいや薬を飲みながら会社に行くオヤジを子どもはどう思うだろうかと思ってしまって。子どもがいなければ、今でも気持ちを押し殺して薬飲みながら会社に通っていたかもしれませんが、息子には幸せそうな親を見て育ってほしいと思って、退職しました。」
会社を辞める前からお世話になっていたコーチにその後も指導を受け、段々に元気になっていく過程で、自分もコーチをやってみようと思うようになった。講座のある学校を紹介してもらって、短いコースを受講してみたところ、コースの最後に「お友達にコーチングをしてみましょう」という課題が出たので、SNSやメールで希望者を集めてみたところ、24人もやりたいという人が現れ、あれよあれよという間に、コーチ業が始まってしまった。
「人にはそれぞれ生まれ持った役割みたいなものがあると思うんですが、自分の本質に気づかずに生きている人は多い。コーチングをしていると、持っているのに出していないというのがわかるんです。どこかでセーブして自分でも認めないようにしているとか、無理をしてごまかしているとか。わかってやっている人もいるけど、分かっていない人の方が多い。
よく人に怒られる人がいるでしょう?怒られている当人は辛いかもしれませんが、その人は怒りたい人の役に立っているという考え方もあると思います。その人らしく自然体でいると、何かしら人の助けになるものなんです。それぞれ社会や他人に供出できるものは違うけれど、はまるものとはまる環境が必ずあるはず。これからも常に学びを深めながら、そういうのを一緒に見つけていきたいと思ってコーチの仕事をしています。」
自分にも人にも求めるモノはユニークネス

長谷の海岸、晩秋のスモーキーな海の色と潮風。波打ち際のカモメが飛び立つ様子にいい笑顔
コーチングの他にも複数の組織に関わっている。がっつり組織に属するのではなく、自分が役立ちそうな場所を見つけて働きを提供する働き方を選んでいるそうだ。交渉力や語学力、海外営業で培ったノウハウがあるゆえのパラレルワーカーとして、自由に楽しく仕事をしていきたいというのが目下のテーマ。
「マネージメントの仕事もしてきましたが、僕は本質的には表現者なんだと気が付きました。人と関わるなら1対1がいいし、グループを相手にする場合も、1対1のスタンスは大事にしています。組織の看板を背負って生きるのではなくて、身一つでできる仕事をして、目の前の人に喜んでもらいたいと思います。コーチングのクライアントでも、自分に対しても一番大事だと思うものは『ユニークネス』だと思う。その人ならではのものを自覚して、自分自身でいること。そのためには内面の深いところまで掘り下げる時間が大事だと思います。いつも組織の代弁ばかりして、誰かの価値観で生きているとだんだんおかしくなってくる。人は自分自身として生きる時間がないと、狂ってしまうと思います。コーチの仕事を通して、人のそういう部分をちゃんと探したい、自分でも探してほしいと思う。
一方で組織でもちゃんと自分を保てる人がいますよね。そういう中身が充実したタイプの人は、組織を背負っても染まらない。会社の意見は会社の意見として理解しているけれど、自分は自分と分けて生きられる。でも中心がしっかりしていないと、お仕着せの衣装のまま与えられた役を演じ続けて、そのうち自分が誰だかわからなくなってしまうんです。自分もそうだった。誰だってたまには信用できる場でそのままの自分を出したり、探求したりする時間が必要だと思います。それがコーチングかもしれないし、他の方法もあるかもしれない。コーチは時として高額なサービスですが、本当にそれが必要な人は、あるいはそれに払う予算がないかもしれないし、そもそもそのサービスの事を知らないかもしれない。そういう人の役に立つにはどうしたらいいか、これからはそういうことも考えていきたいと思っています。」
先々はどうしたいのか、今大いに楽しく考えているそうだが、高校生の頃に夢中でやっていた音楽に立ち返ることも計画に入っているのだそうだ。
「僕は、良くも悪くも表現者なんです。強い力に影響されすぎないように注意しながら、自分であることを見失わないように、自分が何者かを掘り下げていきたい。ミュージシャンになるのも一案です。フリーランスでも収入が安定してきたし、大丈夫だなと思えるようになったので、やりたいことをやり、自分らしく生きながら、家族や周囲の人たちも幸福に自由に生きられるように力を貸したいと思います。」
(テキスト&写真: タコショウカイ モトカワマリコ)
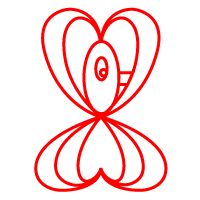

コメントは受け付けていません。